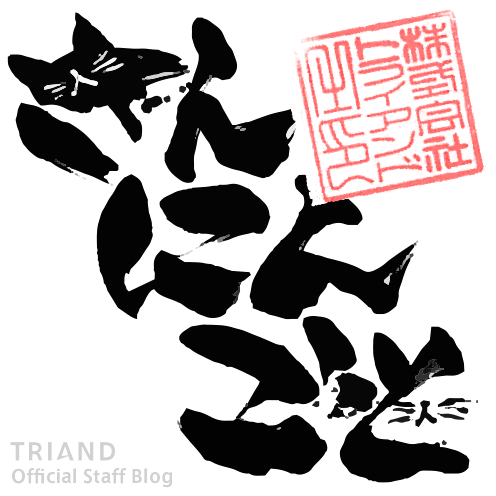コンピュータを使った美術教育
1989年4月。多摩美術大学の上野毛キャンパスに美術学部二部が新設され、「コンピュータを使った美術教育」の授業がスタートした。アップル・ジャパンと産学共同の契約を取り付け、当時1台200万円もしたMacintoshⅡを30台を購入し、須永先生も講師としてヒューマンインターフェイスの授業を担当することになった。1980年代からコンピュータを代表とする思考機能を持った新しい道具が一般生活へ普及したことで、企業がプロダクトデザイナーに対してハードウェアの造形スキルだけではなくソフトウェアの造形スキルも求め始めたのだ。それゆえに、プロダクトデザインの領域から情報デザインの授業がスタートした。人間と道具の触れ合い(ヒューマン・マシン・インターフェイス)と人間と道具の関わり合い(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)である。90年代に入るとソフトウェアの造形スキルを学んだ卒業生は企業側から歓迎される状況が生まれた。
長野オリンピックの裏舞台
1998年2月。情報デザイン学科がスタートする2ヶ月前。1期生の受験シーズン真っ只中に人間の身体能力を最大限に引き出すイベント「長野オリンピック」が日本で開催された。表舞台では身体能力を競い合っていたが、舞台裏では日本のハイテク技術を世界にアピールする側面もあった。カーナビの道路交通情報通信システム(VICS)による最短ルートでの大会関係者の運搬、生体認証(虹彩認識)を取り入れた道具の管理などが挙げられる。そんな日本のハイテク技術をアピールしたサービスの1つに、須永先生がGUIデザイン開発で関わっている。『長野オリンピック ビデオ・オン・デマンド・システム』である。これにより、滑り終わった選手が競技内容を即座に確認でき、観客は見逃した競技内容を保存庫から過去に遡って映像を再生することを可能にした。ハードディスクレコーダとテレビをワンセットにしたものを選手村や駅前に設置し、長野オリンピック限定の映像配信サービスだったと感じられる。
情報デザイン学科の新設
1998年4月。上野毛キャンパスに美術学部二部が新設されてから9年後、多摩美術大学の八王子キャンパスに日本初の情報デザイン学科が新設された。偶然にも翌月の5月には、アップルがスケルトンカラーで有名な伝説の「iMac」を発表する。箱から出して簡単にインターネットに繋げられる特徴は社会基盤にインターネットが急速に浸透することを前提に製造されたように見受けられる。偶然にも9年前に上野毛キャンパスで購入したMacintoshⅡは、スティーブ・ジョブズがアップルを去った後に発売されたパソコンだったことは大変興味深い。
モバイル・インターネットの誕生
翌年の1999年1月。この年はある情報通信技術の産声と共に幕開ける。NTT ドコモが『iモード』を発表したのだ。キャリアメールの送受信やWEBページ閲覧可能な世界初の携帯電話のモバイルインターネットサービスである。常に身につけて持ち歩くことができ、いつでもどこでもインターネットに接続できる端末として捉えれば、ウェアラブルコンピュータの先駆けとしても評価できる。『iモード』はインターネットを持ち歩くことを可能にし、家庭や職場に固定されたパソコンを中心に考えられていたインターネットと人間の関わり合いに変革をもたらした。同年の9月。情報通信技術が発達した未来を描いた映画が公開される。キアヌ・リーブス主演のSF映画『マトリックス』である。仮想空間と現実世界の関わり合いを、身体を媒介にし触れ合うという特徴があった。現代のSNS疲れやLINEいじめといった、仮想空間による現実世界への身体的接触を予期していたのかもしれない。こんな情報通信技術に湧いた時代の中、翌月の10月に情報デザインの国際会議『ビジョンプラス7』が多摩美術大学の上野毛キャンパスで3日間にわたって開催された。
ビジョンプラス7
「情報デザインからコミュニティーの構築を考える」をテーマに、人々の生活と社会活動に結びつく「情報」のはたらきとその在り方について、デザインの視点からさまざまな議論がなされた。目を引くのは、この会議に登壇したスピーカー達の顔ぶれだ。折りたたみ式のノート型パソコンの生みの親であり、IDEOの創設者のひとりでもあるビル・モグリッジ氏。共創(Co-design, Co production)やイノベーションにフォーカスしたデザインリサーチ分野の世界的第一人者であるリズ・サンダース氏。インタラクションデザインという言葉をビル・モグリッジ氏と一緒に考案したGUIデザイナーのビル・バープランク氏。「InDesign」日本語版のソフトウェアデザインを手がけたリン・シェード氏など、そうそうたる面々である。注目したい点は「インターフェイス」をキーワードに語っていたスピーカーが多かったことだ。須永先生も以下のように語っている。
ビジョンプラス7「新しいインターフェイスのモデル」より一部抜粋
情報デザインにおける「インターフェイス」分野が注目される中で、次のデザインの分野を示唆するスピーカーもいた。当時、米国のソニックリム(デザインリサーチ会社)に所属していたリズ・サンダース氏だ。20世紀から21世紀へ。時代と共にデザインの対象も「インターフェイス」から「エクスペリエンス」へと移り変わろうとしていたのである。
ビジョンプラス7 「情報デザインの視野を広げて- 情報から経験へ-」より一部抜粋
肥大化する情報量の分岐点
総務省の情報通信政策局 情報通信経済室が2008年3月に発行した『平成18年度情報流通センサス報告書』の情報流通量等の推移によると10年間で選択可能情報量が約530倍になったのに対して、消費情報量は約64倍に留まっているとの報告がある。1999年(平成11年)にモバイルインターネットが誕生し、2001年(平成13年)にYahoo!BBがブロードバンドに参入したことで日本の情報量が爆発した。しかし、人間の情報処理能力が情報量に比例して向上したりはしない。これは人間の身体的な制限に関係する。電気信号の伝達速度が約秒速30万kmに対して、神経細胞の伝達速度は約時速100〜400kmなので情報量が肥大化したら処理が追いつかないのだ。したがって、情報量の増大は人間の認知的な負荷が高くなる。例えば、未読件数が膨れ上がり大切なメールを見逃す危険性があるGmaiの受信トレイである。それゆえ、最近は自動でメールを仕分ける機能が付いたのだろう。
上記の報告書からも平成11年がグラフが急上昇していない最後の年と見てとれる。これ以降は情報量が膨れ上がり物理的に全ての情報を追うことは不可能となる。こういった技術先行型社会の在り方に警鐘をならし、人間がもっと豊かな生活を過ごす未来を描くために須永先生の研究対象が「インターフェイス」から「エクスペリエンス」へ移っていく。筆者が大学に入学したころには「人間の活動を基板としたデザイン開発」と呼ばれていた。しかし、『ビジョンプラス7』が開催された1999年10月は高校1年制の秋で麻雀に明け暮れる日々を過ごしており、当然、須永先生ともまだ出会ってもいなかった。(hiranotomoki)
==================
参考文献
多摩美術大学におけるコンピュータ教育の沿革 高橋士郎
PROVOKE デザイン・インフォマティクス・フォーラム
長野冬季オリンピック・パラリンピックとデザイン
ビジョンプラス7
よい製品とは何か
==================
目次(予定)
1:インターフェイスからの転換期
2:エクスペリエンスの描き方
2:サービスのデザイン
4:情報デザイン
5:インタラクション元年 任天堂wiiとiPhoneの発売
エピローグ
==================